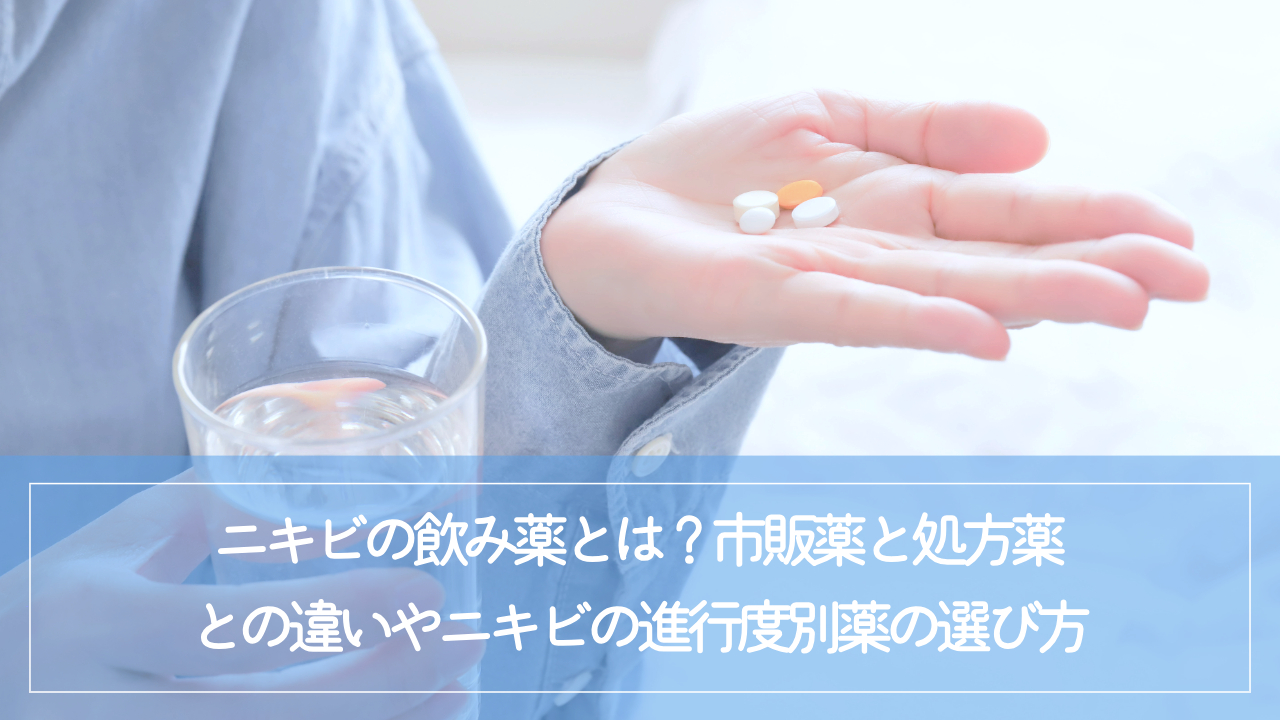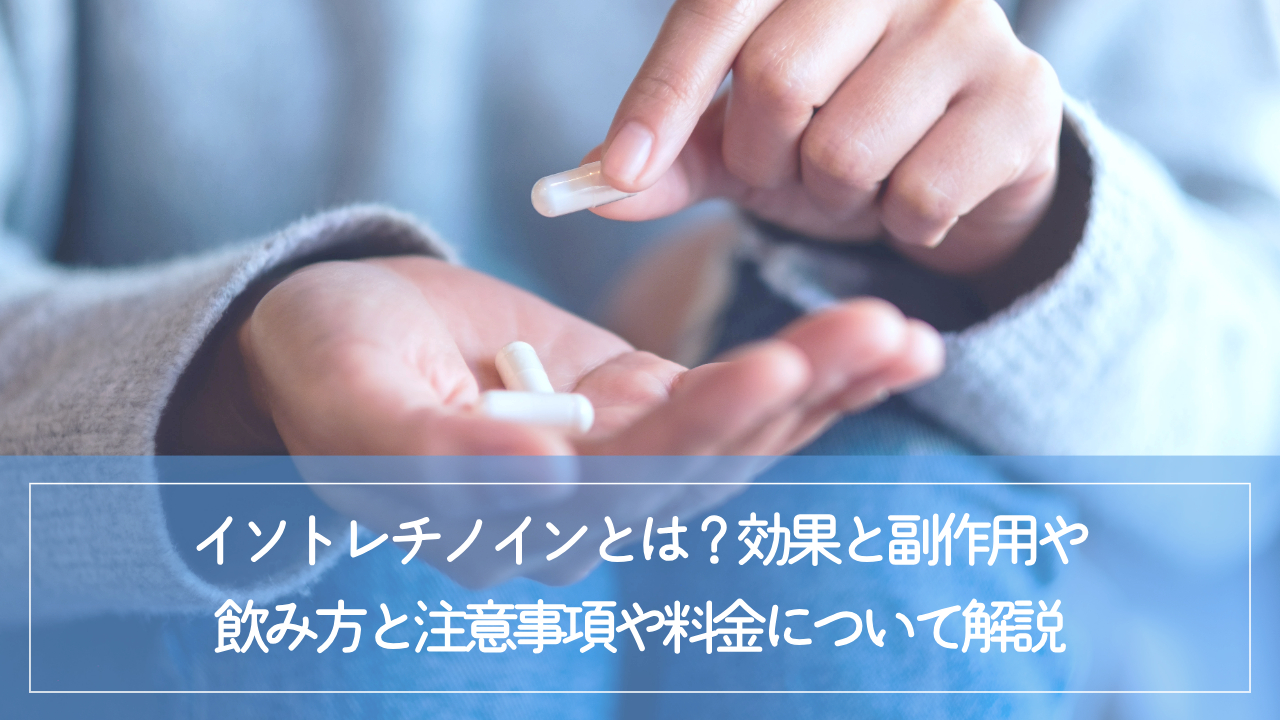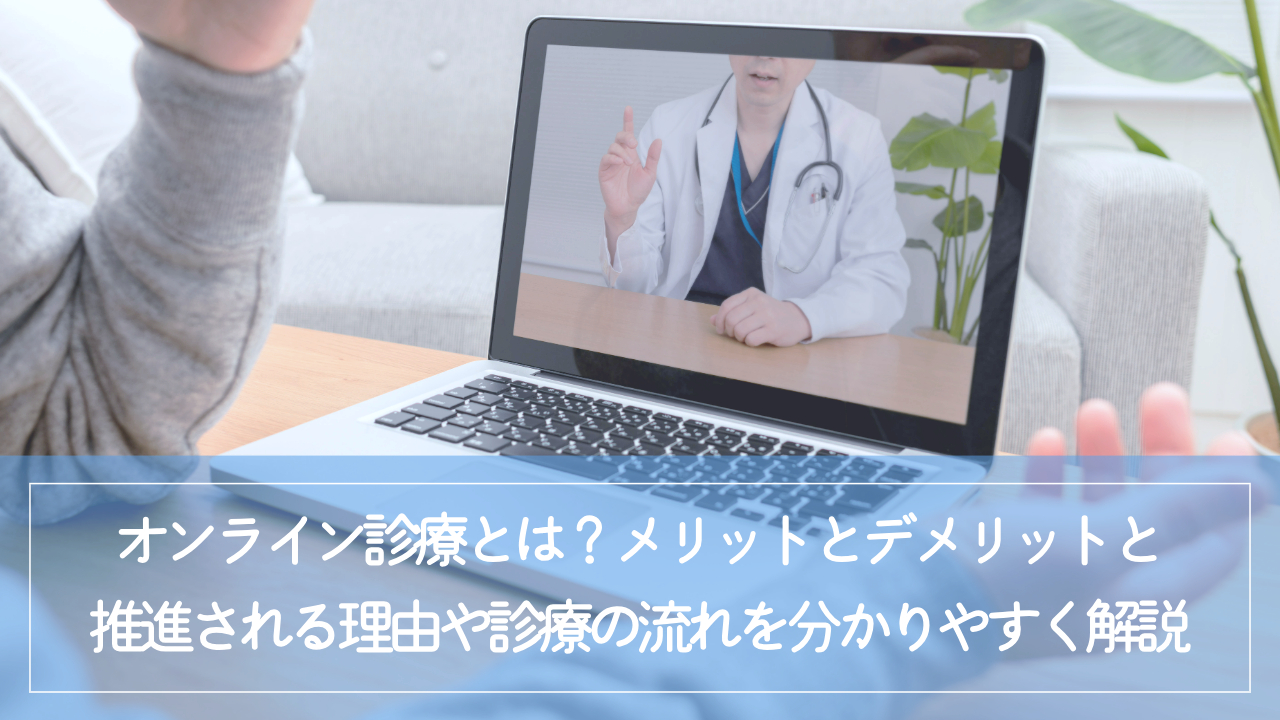ニキビの飲み薬を選ぶ際は、ニキビの進行度に合わせて薬を選ぶ必要があります。
ニキビの飲み薬には、市販薬と処方薬がありますが、どんな薬があり、どの薬を選ぶべきか悩む場合もあるかもしれません。
適切なニキビの飲み薬を知るために、市販薬と処方薬の違いや、ニキビの飲み薬の種類について確認してみましょう。
ニキビの飲み薬とニキビの進行度
ニキビの治療に飲み薬を使用する場合もあるかもしれません。
ニキビの飲み薬を選ぶ際は、ニキビの進行度を知り、進行度に合わせて薬を選ぶ必要があります。
ニキビは、白ニキビ、黒ニキビ、赤ニキビ、黄ニキビの順に悪化して行きます。
- 白ニキビ白ニキビの段階では、アクネ菌に対する抗菌が不要なため市販薬でも対応が可能です
- 黒ニキビ黒ニキビの段階では、アクネ菌に対する抗菌が不要なため市販薬でも対応が可能です
- 赤ニキビ赤ニキビの段階では、ニキビに炎症が起きているため「抗炎症成分」や、アクネ菌に対する「抗菌成分」が含まれる薬が必要なため、医師による処方薬が必要になります
- 黄ニキビ黄ニキビの段階では、ニキビが化膿しているため、「抗菌成分」による治療が必要になり、医師による処方薬が必要になります。また、飲み薬だけでなく、塗り薬などの外用薬も併用する場合があります
白ニキビと黒ニキビの段階では、市販薬でも対応が可能ですが、赤ニキビと黄ニキビの段階では、市販薬を使用しても効果が期待できないため、処方薬での治療が必要になります。
ニキビの飲み薬の市販薬と処方薬の違い
ニキビの飲み薬の市販薬と処方薬の違いについて確認してみましょう。
ニキビの飲み薬の市販薬は、肌のターンオーバーや肌の老廃物の排出を促すことで、肌状態を整えます。
一方で、ニキビの飲み薬の処方薬は、皮脂の分泌を抑える作用、アクネ菌に対する抗菌作用、抗炎症作用があり、ニキビの原因の根本的な治療を行います。
また、市販薬の購入は薬局やドラッグストアなどで可能ですが、処方薬の購入には医師による診断と処方せんが必要になります。
ニキビの飲み薬のおすすめの市販薬
白ニキビと黒ニキビに効果が期待できる、市販薬の飲み薬について確認してみましょう。
白ニキビと黒ニキビには、肌のターンオーバーを整え、肌の老廃物の排出を促し、毛穴づまりを改善する、ビタミンB1、B2、B6を摂取するようにしましょう。
また、皮脂が気になる場合は皮脂分泌を整える、ビタミンB2を摂取するようにしましょう。
さらに、漢方薬を選ぶ場合は、毛穴づまりを改善するヨクイニンや、皮脂の排出を助け肌のざらつきを改善するケイヒ、血行促進と抗炎症作用のあるキキョウが良いでしょう。
ハイチオールBクリア
ハイチオールBクリアは、ビタミンB群やビタミンC、肌のターンオーバーに関わるL-システインを配合した飲み薬で、思春期や大人の肌あれやニキビが気になる人におすすめです。
肌のターンオーバーの正常化を導いて、ニキビの改善を促し、キメの整った肌へと導きます。
また、脂質の代謝とコラーゲンの生成をサポートし、肌のバリア機能が整った健全な肌へと整えます。
- 分類:第3類医薬品
- ビタミンB2配合量:38mg
- ビタミンB6配合量:50mg
- 有効成分:L-システイン、リボフラビンリン酸エステルナトリウム、ピリドキシン塩酸
- 塩、チアミン硝化物、ニコチン酸アミド、ビオチン、パントテン酸カルシウム、アスコルビン酸
- 服用回数:1日1回、1回3錠(15歳以上)、1回2錠(11歳~14歳)
※11歳未満は服用しないこと
(参考)エスエス製薬「ハイチオールBクリア」
チョコラBBプラス
チョコラBBプラスは、B群ビタミン(B2・B6・B1)を高単位に配合し、体の中で直接働く活性型ビタミンB2が、肌細胞の生まれ変わりをサポートし、ターンオーバーの正常化を促し、肌あれ、にきび、口内炎をケアします。
ターンオーバーを促し、毛穴づまりや「角栓」ができにくくすることで、ニキビ予防の効果も期待できます。
- 分類:第3類医薬品
- ビタミンB2配合量:38mg
- ビタミンB1配合量:20mg
- ビタミンB6配合量:50mg
- パントテン酸カルシウム:20mg
- ニコチン酸アミド:40mg
- 服用回数:1日2回、1回1錠(15歳以上)
※15歳未満は服用しないこと
(参考)エーザイ「チョコラBBプラス」
ビタミンBBプラス「クニヒロ」
ビタミンBBプラス「クニヒロ」は、体内で吸収されやすい補酵素型のビタミンB2リン酸エステルを主成分に、肌に関係する4種類のビタミンB群、ビタミンB6、B1、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウムを配合しています。
ビタミンB2は皮膚の皮脂腺の働きを調節し、B6がB2と働き合って皮膚のターンオーバーを促進し、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウムとともに皮膚や粘膜の症状を正常化します。合成着色料は不使用です。
- 分類:第3類医薬品
- ビタミンB2配合量:38mg
- ビタミンB6配合量:50mg
- ビタミンB1配合量:20mg
- ニコチン酸アミド:40mg
- パントテン酸カルシウム:20mg
- 服用回数:1日2回、1回1錠(15歳以上)
※15歳未満は服用しないこと
(参考)皇漢堂製薬「ビタミンBBプラス『クニヒロ』」
ネオ小町錠
ネオ小町錠は、12種類の生薬に5種類のビタミン、ビタミンB2・B6、ビタミンCなどに加え、必須アミノ酸のメチオニンを配合し、生薬の働きで肌の老廃物や膿の排出を促しながら、肌に必要な成分を補うことで、ターンオーバーを整えます。
継続的に服用することで、ニキビ予防や、ニキビができにくい肌へ整えます。
- 分類:第2類医薬品
- ビタミンB2配合量:5mg
- ビタミンB6配合量:20mg
- 有効成分:キキョウ、センキュウ、ダイオウ、オウゴン、トウキ、ボタンピ、ヨクイニン、ケイヒ、ケイガイ、レンギョウ、サンキライ、ニンドウ、ニコチン酸アミド、リボフラビン、ピリドキシン塩酸塩、アスコルビン酸、DL-メチオニン、パントテン酸カルシウム、乳酸カルシウム水和物
- 服用回数:1日2~3回、1回3~5錠
※5歳未満は服用しないこと
※小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください
(参考)耶堂製薬「ネオ小町錠」
ペア漢方エキス錠
ペア漢方エキス錠は、5つの生薬でホルモンバランスを整え、生理前に繰り返すニキビの改善や、ニキビができにくい状態へ導く漢方薬です。
また、血のめぐりを改善することで、ターンオーバーの正常化を促進し、大人ニキビやシミの改善が期待できます。
- 分類:第2類医薬品
- 有効成分:ケイヒ末、ブクリョウ末 、ボタンピ末 、トウニン末 、シャクヤク末
- 服用回数:1日2回、1回4錠
※15歳未満は服用しないこと
(参考)ライオン「ペア漢方エキス錠」
ニキビの飲み薬のおすすめの処方薬
処方薬とは、医療用医薬品のことで、病院や診療所などで、医師が診断しを行い発行した「処方箋(しょほうせん)」に基づいて、薬剤師が調剤する薬を指します。
ニキビの処方薬とは、医師の診断のもとニキビに効果が期待できるという、医療的根拠に基づいて、処方される薬のことで、主に「抗菌薬」と「漢方薬」があります。
また、海外では重症ニキビの治療薬として一般的に「イソトレチノイン」が用いられますが、日本では未承認のため保険適用外での処方となります。
抗菌薬
赤ニキビでは、アクネ菌などのニキビ菌への対策と、ニキビの炎症を抑制することが大切です。
赤ニキビへの抗菌薬としては主に、ドキシサイクリン、ミノサイクリン、ロキシスロマイシンが有効とされています。
ただし、光線過敏や、腸内細菌まで殺菌するため下痢の副作用があります。
また、「薬剤耐性菌」の発生を防ぐために、継続しての服用は3ヶ月以内とすることが推奨されています。
漢方薬
漢方薬は、抗菌薬を長期間内服することで起こる「薬剤耐性菌」の発生が懸念される場合や、抗菌薬を内服しても効果が得られなかった場合に用いられます。
赤ニキビでは、荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)、清上防風湯(せいじょうぼうふうとう)、十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)を、白ニキビでは、荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)を用います。
漢方薬は、細菌感染の抑制や炎症の改善が期待できますが、ニキビの進行度によって使用する漢方薬が異なるため、医療機関を受診しするようにしましょう。
イソトレチノイン
イソトレチノイン(isotretinoin)とは、ビタミンAとその誘導体を合せたレチノイドを主成分としたニキビ治療用の内服薬です。
イソトレチノインの主成分である、ビタミンAとその誘導体を合せたレチノイドには、皮脂の分泌を抑える作用、アクネ菌に対する抗菌作用、抗炎症作用があるため、重症ニキビに対して効果があるとされています。
また、イソトレチノインはニキビ治療に高い治療効果がある他、内服を終了した後にもニキビの抑制効果が期待できます。
アメリカをはじめとした海外では、重症ニキビに対する治療薬として承認されている歴史ある治療薬ですが、日本では厚生労働省の認可がおりていないため、保険が適応されず、自由診療での治療となります。
▼「イソトレチノイン」についてさらに詳しく
イソトレチノインとは?効果と副作用や飲み方と注意事項や料金について解説
ニキビの飲み薬の注意点
ニキビの飲み薬を内服する際の注意点について確認してみましょう。
- 用法・用量を守る
- 薬との飲み合わせについて医師・薬剤師に相談する
- 改善しない場合は皮膚科を受診する
- 自己判断による服用開始、中断、または変更は行わない
用法・用量を守る
内服薬は、年齢や体重によって用量が異なります。また、用法・用量を守らずに内服することで、十分な効果が得られなかったり、副作用が現れる場合があります。
薬との飲み合わせについて医師 薬剤師に相談する
すでに、何らかの薬を内服している場合、薬の組み合わせによっては、効果を下げたり作用を高め合ったりする場合があります。複数の薬を内服する場合には、薬の飲み合わせについて医師や薬剤師に相談するようにしましょう。
改善しない場合は皮膚科を受診する
市販薬を内服しても、ニキビが改善しなかったり、悪化した場合には、皮膚科を受診するようにしましょう。また、赤ニキビなど市販薬では抑えることが難しいニキビの場合、放置することで、ニキビ跡になってしまう場合もあるため、皮膚科の受診を早めにする方が良いでしょう。
自己判断による服用開始、中断、または変更は行わない
処方薬を内服している場合は、治療の効果を最大にしてリスクを最小に抑えるためにも、処方薬の内服に問題がなければ、医師が指導した通りの治療を続けるようにしましょう。処方薬を内服したことで、効果が出てきたからと、内服を中止してしまうことで、ニキビ再発のリスクが高まります。
まずは医師の診断からスタートする

\ご相談のみも歓迎/
今すぐ無料診察を予約する